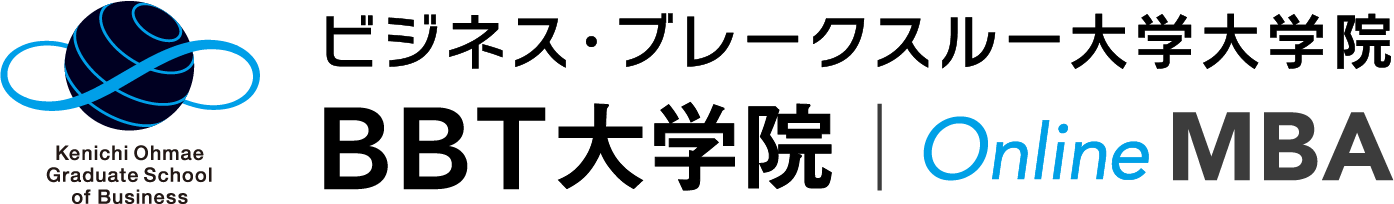第3次世界大戦につながる道なのか?

大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
ハマスとイスラエルの戦いに終結の兆しが見えません。2023年12月の記事の中で、「第3次世界大戦へつながる破滅の道」という最悪のシナリオをBBT大学院・大前研一学長は警告しました。
【資料】大前研一案:中立国がガザ地区を信託統治して、中東に和平を取り戻す
昨今の情勢は悪化する一途です。1歩どころか2歩も3歩も第3次世界大戦へのシナリオに近づいています。
米国とイランの代理戦争の様相
世界は、破滅の道を突き進むのか。鍵を握るのは、ハマスとイスラエルの戦いへ米国が本格参戦するか否かである。
2024年1月28日、ヨルダン北東部の米軍基地にドローンによる攻撃があり、米兵3人が死亡したと米政府当局が発表した。攻撃したのは、イラクの武装組織「神の党旅団(カタイブ・ヒズボラ)」と見られている。イスラエルとハマスが2023年10月に衝突して以来、中東では米軍基地がたびたび攻撃されていたが、米兵の死者が出たのは初めてだ。
同年2月8日、こんどは米軍がイラクの首都バグダッドに、英軍と共同でドローンによる「報復攻撃」を行った。この攻撃で、神の党旅団の司令官を含む3人を殺害している。
ここで問題なのが、神の党旅団の後ろにはイランがいることだ。両勢力の報復攻撃がエスカレートすれば、今後米国とイランの直接戦闘に発展していくおそれがあるからである。
最高指導者アリー・ハーメネイー氏率いるイランが支えるのは、神の党旅団だけではない。ガザのハマスや、レバノンのヒズボラも後ろ盾はイランだ。また、イエメンの反政府勢力であるフーシ派も、イランの支援を受けている。
米国が本格参戦しても、短期間では決着しない
一方、イスラエルの後ろには米国が控える。米国とイランが事を構えるなら、「世界最強」の軍隊を擁する米国優位と見る向きが多い。
しかし、米国の参戦で戦闘に決着がつくと考えるのは大間違いだ。米軍はそのイメージとは裏腹に、ベトナム戦争以降は敗戦を重ねている。
アフガニスタンが良い例だ。2001年、米国同時多発テロの首謀者オサマ・ビンラディンをかくまっているとして、アフガニスタンを支配していたタリバンを米国は攻撃した。しかし、タリバンは壊滅に至らず、肝心のオサマ・ビンラディンはアフガニスタンではなくパキスタンに潜伏していた。CIAなどで高名な米国の諜報力が、実は貧弱であることが露呈している。
その後、一時は弱体化したタリバンは徐々に勢力を回復し、脅威に感じた米国は2021年にアフガニスタンから完全撤退。20年にわたる軍事攻撃は、派兵した米国とその同盟国に多くの戦死者を出しただけに終わった。
世界中から嫌われている米国
米国とイランが本格的に衝突すれば、アフガニスタンと同様の展開が予想される。イランがしぶとく粘るうちに戦闘が長期化して、お互いに疲弊していくに違いない。
また、米国にとってはイラン以外にも敵が大勢いることが頭痛の種だ。
イランが直接支援するハマス、ヒズボラ、フーシ派だけではなく、シリアやそれを支援するロシア、シリアに拠点を置くISなど、米国は多方面で緊張を強いられている。日本にいると見えてこないが、米国は世界中で嫌われている国なのである。
米国が嫌われるのは、「自らが信じる正義」を無理やり押しつけるからだ。わかりやすい例はイラクである。
イスラム教を国教とするイラクは、国民の大多数をシーア派が占めている。一方、1979年から03年までイラクを治めていたサダム・フセイン大統領は、国内で少数派のスンニ派だった。フセイン政権は強権的な統治だったが、少数派が多数派を支配するには独裁者になるしかないという、政治的なリアリズムを発揮しただけの話である。
ところが、米国の正義感は独裁者を許さない。2003年、コリン・パウエル米国務長官(当時)は国連で「イラクは大量破壊兵器を保有している」と演説した。イラクへの軍事攻撃を正当化したアメリカは、同年にサダム・フセインを捕らえて後に処刑したが、後年になってイラクは大量破壊兵器を保有していなかったことが判明した。
そして、イラクで戦争を始めた米国は、重大な誤りを犯したことに気づく。サダム・フセインの追放後、イラクで米国が大好きな「民主化」選挙をやったところ、反米のシーア派政権が誕生した。米国はわざわざ自分の敵を増やすために、その国の国民を独裁者から「解放」したわけだ。
同じことは、エジプトでも起きている。2011年に独裁者のホスニー・ムバラク大統領を「アラブの春」で失脚させたが、その後の選挙では反米のムスリム同胞団がつくった政党が勝利し、モルシ内閣が発足した。その政権もすぐに頓挫して、軍事クーデターが発生。今となっては、ムバラク時代よりも強権的なシーシー政権が誕生している。
そもそも、米国とイランの仲が悪くなったのは、1979年のイラン革命で失脚した国王パフラヴィー2世を米国に亡命させ、イラン革命政府の引き渡し要求に応じなかったからである。
革命後のイランの最高指導者は、初代がルーホッラー・ホメイニー氏、2代目は現職のハーメネイー氏。米国との関係は一貫して冷え込んでおり、革命から40年以上経った今でもイラン国民は「自分たちが孤立しているのは米国のせいだ」と恨み骨髄だ。
第2次大戦後、日独伊の「民主主義化」に成功した米国の体験が仇
米国には、「自分が嫌われているのは自業自得である」という意識がない。むしろ博愛主義的に、「現地の民衆に良いことをした」とさえ思っている。
そのような勘違いをしている一因は、日本にもある。米国は太平洋戦争で日本を軍国主義から解放し、そのおかげで戦後は素晴らしい民主主義国家になったと多くの日本人は信じている。
日本やドイツ、イタリアなどでの「民主主義化」の成功体験をいいことに、世界中でお節介を繰り返した結果、米国は自らの手で数多くの反米地域をつくり出した。身から出た錆である。
2024年の米大統領選挙戦が「強い米国」を煽る
米国も、本当は戦争に懲りている。ウクライナ支援のように、人を出さずに武器だけを渡して、軍需産業が儲かる形をつくれたらいいが、第3次世界大戦になればそうはいかなくなる。現在のイスラエルとハマスの戦いに、できれば巻き込まれたくないというのが多くの米国人の本音である。
しかし、2024年はタイミングが悪いことに米大統領選挙が控えている。トランプ前大統領は、バイデン大統領が慎重さを見せた途端、執拗に批判する。トランプ氏は弁が立つので、次第に国民も煽られて、選挙戦が進むとともに「イランは許しがたい」という声が高まってくる。そして、背中を押されたバイデン大統領は、何か勇ましいことを言わざるをえなくなる。米国の国内政治を考慮しても、第3次世界大戦のリスクは高まっていると言える。
気になるのは、NATO加盟国の動きである。英国は米国に同調するだろうが、欧州大陸は基本的に静観の構えだ。フランスは米国に「イランを無視してほしい」と考えている。
NATO加盟国で一番したたかなのはトルコだ。表立って反米的な動きはしないものの、国民の大半がイスラム教徒であるがゆえに、心情的にはイラン寄り。いずれにしても、NATO加盟国は親米の一枚岩ではない。
一方、イランとしては米国と対立関係にあるロシアや中国を自陣営に引き込みたいところだが、ロシアはウクライナとの戦争で疲弊していて余裕がない。中国も現時点でどこまでイランに肩入れするかは不透明である。
「米国の敵まで自動的に日本の敵」に陥る愚を避けよ
このような混沌とした国際情勢の中で、日本はどのような外交戦略をとるべきか。私は、現在のように米国にべったりの姿勢は見直すべきだと思う。米国はアフガニスタンで、同盟国を見捨てて一目散に撤退した。急な撤退で、日本大使館の職員は脱出に相当苦労したと聞く。そのような薄情な国を、全面的に信頼するのは危険だ。
もともと日本はイランとの仲が悪くない。戦後、イギリスと抗争中のイランから出光興産が石油を輸入したり、高度経済成長期以降は多くの日本企業が首都テヘランに進出するなど、経済面での結びつきが強かった。三井物産などは、6000億円を超える投資で巨大なコンビナートを建設する計画を立てた。イラン革命で米国とイランの関係が悪化したあとは、日本もイラン制裁に加わらざるをえなかったが、現在でもイラン人の対日感情は悪くない。これ以上、米国に追従して日本がイランと関係を悪化させる必要はない。
他の国との関係も同じだ。ロシアのプーチン大統領は国際的に孤立して四面楚歌の状態だ。日本とロシアはいまだに平和条約を結んでいないが、今話を持ちかければロシアは高い確率で乗ってくるだろう。平和条約が締結できれば、ロシアの軍事的な脅威は減る。さらに、ロシアに急接近している北朝鮮も日本に手を出しにくくなるだろう。
また、中国とは2000年にわたる外交の歴史に基づいて仲良くすればいい。米国の子分として、日本が米中対立の矢面に立つ必要はない。
もちろん米国とも引き続き仲良くすればいい。しかしベッタリしすぎた結果、米国の敵まで自動的に日本の敵に陥る愚は避けたい。
世界は着実に第3次世界大戦へと進みつつある。危機だからこそ、はじめて現実感を持って考えられるという面もある。新しい地政学の中で、どのように振る舞うべきか。日本の外交関係を見直す契機としてもらいたい。
※この記事は、『プレジデント』誌 2024年3月29日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。