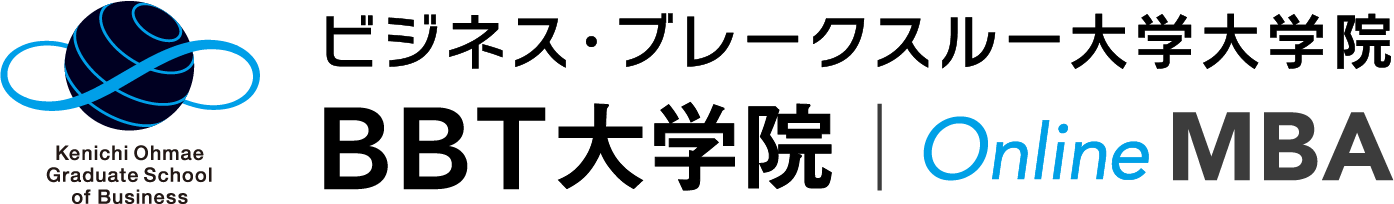4万円を超えた日本株価は、上昇を続けるのか?

大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
2024年2月22日、日経平均株価(日経225)は1989年の大納会(12月29日)に記録した史上最高値、3万8915円を約34年ぶりに更新しました。その後も日経平均株価は上昇を続け、2024年3月4日には4万円の大台に初めて乗りました。
日本株高を受けて、新聞などでは「“失われた30年”が終わった」という論調が目立ちます。しかし、安堵するのは間違いです。最高値更新は見せかけであり、日本を蝕む根本的な問題は解決されていません。“失われた30年”は今後も続くとBBT大学院・大前研一学長は言います。「最高値更新は見せかけ」「“失われた30年”は今後も続く」と言える理由は何か。大前学長に聞きました。
「史上最高値更新」には、2つのインチキがある。順番に説明しよう。
日経平均株価という物差しがインチキ
まず、日経平均株価という物差しがインチキだ。日経平均株価は、東証プライム市場に上場する約1650銘柄の株価や時価総額の平均ではなく、日本経済新聞社が選んだ225銘柄の株価合計を銘柄数で除したものだ。構成銘柄はSMC(2022年に採用)やキーエンス(同2021年)などの単元株価の高い「値がさ株」に次々に入れ替えられ、その影響が強く出る計算方式である。
バブル期と現在の株価を正確に比較するなら、本来はずっと同じ銘柄で比べる連続性が必要である。しかし、1991年からは倒産や合併以外の理由でも構成銘柄を「値がさ株」に入れ替え始めた。2000年以降は「値がさ株」への入れ替えを毎年定期的に行っている。
【資料1】日経平均株価銘柄変更履歴(2023/10/2現在)
構成銘柄の中身が入れ替わっていれば、もはや物差しとしては役に立たない。業績好調の銘柄ばかりを新規に採用するのだから、日経平均株価は上がって当然だ。何ら喜ぶようなことではない。
【資料2】株式ランキング(単元株価格上位)
3万8915円そのものがインチキ
史上最高値更新には、もう一つインチキがある。34年前につけた、3万8915円そのものがインチキなのだ。
日経平均株価が初の3万円台に突入した1888年12月頃から、証券会社やマスコミはこぞって「株価はもっと上がる」と煽った。「6万円台になる」と言い放ったエコノミストもいた。日本は資源のない国だが、情報化社会に突入すればそれが追い風になり、「日本に世界中の情報が集まって独り勝ちする」という論法だ。1880年代にベストセラーになったエズラ・ヴォーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバーワン』とアルビン・トフラーの『第三の波』の内容を都合よく切り貼りしたような主張である。
しかし、それは絵に描いた餅である。日本中がバブルで浮かれている頃、私は企業が将来得る利益を現在価値で割り戻す「収益還元価格法」を用いて、日本企業の本当の価値を計算した。収益還元価格法の結果から日経平均株価を算出すると、1万2000円という数字になった。なお、これはバブルが継続した場合の価値で、バブルが崩壊すれば9000円台になる。この計算結果を知った不動産会社やバブル紳士からは、「不吉なことを言うな」と脅された。
不吉も何も、私は今ではM&Aにも使われる手法で冷静に企業価値を計算しただけである。むしろ根拠のない「予想」をしていたのは証券会社やマスコミだ。証券会社は自ら希望的観測に満ちた予想をして、「株価はこうなりますから今買わないと損」と中金持ちの尻を叩いた。34年前の3万8915円は、そうやって人為的につくられた株価だった。
その後、2008年、日経平均株価はバブル後の最安値となる6994円まで下落した。私の「計算」が正しかったことが証明されている。
日経平均株価の上昇の理由は、米国の株高
物差しの不正確さに目をつぶったとしても、今回の最高値更新は喜べない。株価の上昇は、日本の実体経済が良くなったことが理由ではないからだ。
日経平均株価上昇の背景にあるのは、米国の株高だ。米国の代表的な株価指標の一つS&P500種指数は、2024年2月に史上初の5000ポイントを超えた。通常、株価が上がると、次は不動産にマネーが流れる。しかし、米国は不動産市場がすでに下降局面で、行き場を失ったマネーが世界中に分散投資されている。
「世界中」と言っても、欧州は元気がない。また、中国からは逆にマネーが逃げている。そこで世界の投資家が選んだのが、インドと日本。日本企業は相変わらず死に体だが、急に天から精力剤を注入されたようなものだ。
バケツに水を注げば水面が上がるのは当然で、株価の上昇を楽しんだ投資家は頃合いを見て利食いをするだろう。その水を注ぐ代表が、バークシャー・ハサウェイ会長のウォーレン・バフェット氏だ。「日本のインデックス」のような5大商社株を買う動きに、他の投資家が便乗した感がある。
さらに、百歩譲って「世界の投資家が日本企業を正しく評価して株を買っているのだ」としても、それはまったく自慢にならない。
日本は約34年かけて株価をバブル期の最高値に戻した。同じ34年間で他国の株価上昇度合いを比べると愕然とする。米国のS&P500種指数は、1989年12月29日の終値が353.40ポイント。2024年2月22日の終値が5087.03ポイントだから、低迷する日本株が株価を元に戻す間に、米国株の株価は約14.4倍になっている。ドイツ株価指数も同じように計算すると、約9.7倍だ。
史上最高値と浮かれている場合ではない。成長する他国をよそに、株価を過去の数値に戻しただけの情けない話なのである。
「失われた30年」が今後も続く理由
私が「失われた30年」は続くと考える理由は、バブル崩壊に懲りた結果、変質してしまった「日本人」そのものが変わっていないからだ。
バブル崩壊のきっかけは、金融機関に対する窓口指導・総量規制だ。バブルで不動産価格が上昇して「サラリーマンが住宅を買えなくなる」と野党が騒ぎ、金融機関の貸し出しに規制をかけた。そこから不動産価格が下がっていき、バブルが弾けた。融資を規制された銀行は傘下のノンバンク経由で金を貸していた。そのノンバンクもひっくり返り、多額の不良債権を抱えることに。
そして、政府は金融システム安定のために、230兆円もの公的資金を注入した。公的資金とは、とどのつまり国民負担である。日本国民は、バブル崩壊の清算で大きなツケを払うことになったのだ。
何か痛い目に遭っても「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で、しばらくすれば再び活発に消費し始めるのが世界標準である。リーマンショックの震源地だったのに、相変わらず平気で借金をして、旺盛に消費する米国がいい例だ。ところが、日本人は「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」ですっかり意気消沈してしまい、物を所有する欲がなくなった。
バブル崩壊前の日本人は、所有欲が日々の生活の原動力になっていた。サラリーマンは通勤に1時間20分かかるとしても、郊外にマイホームを買った。「都心から遠いと座れるからいい」とうそぶいて、長時間の通勤に耐えた。
また、多くの人が別荘を持つという夢を抱いていた。戸建ての別荘は無理でも、伊豆高原のリゾートマンションであれば手が届く。憧れの別荘を手に入れるために残業を厭わず働いて、高い金利を払って買ったのだ。
しかし、今の日本人は違う。家は職場に近いほど良くて、狭い賃貸で十分。別荘を持つ発想はなく、近場の温泉地に1泊できれば満足だ。たまに観光地に行っても、お金を使わない。人がすっかり変わってしまったようだ。
欲を失ったのは消費者だけではない。企業も同様で、成長のために借金して投資をする発想が弱くなってしまった。消費者と企業の低欲望化が、“失われた30年”の真因である。
政府が打ち出す景気浮揚政策は見当はずれ
政府はこのことがわかっていないから、見当はずれの政策ばかり行ってしまう。愚策の筆頭が、金利を払えない企業を延命させた「亀井モラトリアム」と、異次元金融緩和の「アベクロバズーカ」(アベノミクス)だ。いくら企業がお金を借りやすくしたところで、成長の意欲がなければ投資は進まない。むしろ何もしないで生き延びられる状況をつくったことで、企業はますます投資の意欲を減退させてしまった。
個人に対する政策も間違いだ。政府は消費が伸びないのは所得が少ないからだと言って、企業に賃上げを要請している。しかし日本人の個人金融資産は増え続け、2023年に2100兆円を突破した。中高年はお金があっても増やそうとはしないで、0.001%しか利息のつかない預金口座に“安置”し、消費しようともしない。一方、若い世代はたしかにお金がないが、そもそも物欲がなく、稼ぐ意欲も低い。無理に賃上げしたところで、個人金融資産をさらに積み上げるだけだ。
国民や企業の、失われた欲望を喚起せよ
政府が最優先で取り組むべき政策は、日本人に欲望を取り戻させることである。具体的には、お金を使いたい人の邪魔をしないことが大切だ。未婚化・少子化が続いているが、若い人の中にも結婚して子どもを持ちたい人はいる。
日本人の欲望を刺激するために、欲がある海外の人や企業を呼び込むことも重要だ。オーストラリアやカナダはお金を持ち込んでくる外国人に永住権や市民権を与え、お金はないものの上昇志向が強い外国人には国費で教育を施し、成績が良い人を受け入れる。そうした外国人の経済活動は、国内経済を直接回すだけでなく、もともとの国民の欲望にも火をつけてくれる。
政府は次々に景気対策を打ち出しているが、それらは経済刺激策ではない急場しのぎで、見当違いの政策だ。より根本的な政策は、国民や企業の失われた欲望を喚起することである。より良い人生を謳歌したいという欲望に支えられて、消費や投資が活発になり、企業が利益を上げる。それを反映して、株価が上がっていく——。この流れをつくれない限り、「失われた30年」は永遠に打破することができないことを、政府は早急に自覚するべきだ。
※この記事は、『プレジデント』誌 2024年4月12日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。