第2次トランプ政権を閣僚人事の顔ぶれから占う
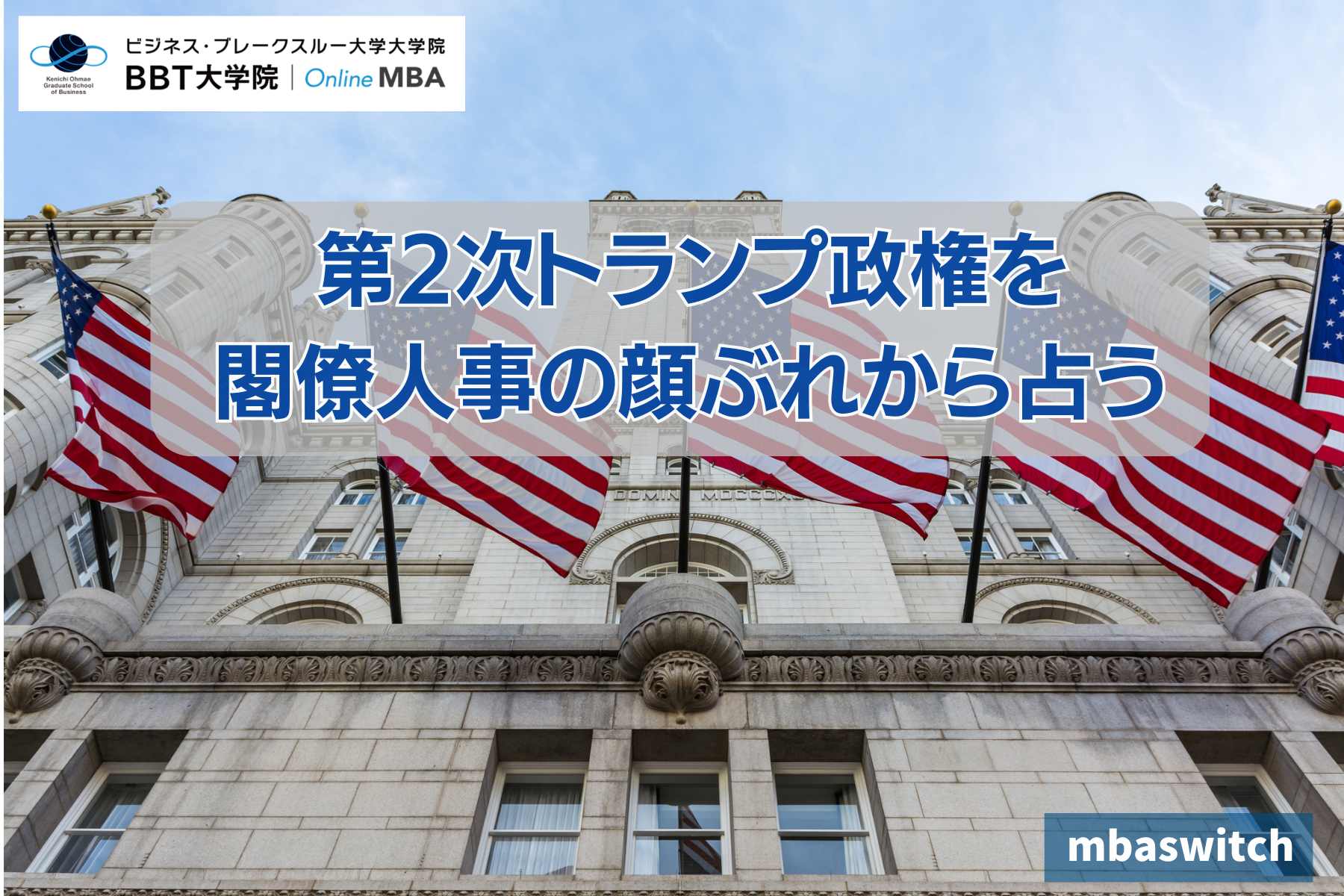
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
トランプ政権が2025年1月20日に発足しました。トランプ大統領が指名した主要人事は【資料】のような顔ぶれです。閣僚など上級職の任命をめぐっては承認が必要となるため、上院で承認の手続きが順次進められているところです。
第2次トランプ政権の閣僚人事には、第1次トランプ政権の閣僚人事を反省しているあとが見られるとBBT大学院・大前研一学長は指摘します。第2次トランプ政権を、閣僚人事の顔ぶれから占ってみます。
第2次トランプ政権の閣僚たちはトランプ氏のクローン人間
厚生長官に指名されたロバート・ケネディ・ジュニア氏は、上院本会議で最終承認に向けた採決が実施される見通しである。ケネディ氏はワクチン懐疑論者で、小児用ワクチン接種の廃止を目論んでいる。ノーベル賞受賞者77人がこの人事に反対する書簡を上院に送った。
司法長官にはフロリダ州前司法長官のパム・ボンディ氏が就任した。司法長官に最初に起用したマット・ゲイツ前下院議員は、児童買春をした疑いのある人物とされる。エプスタイン事件への関与が疑われるトランプ氏はこれを気にしなかったのだろうが、共和党内から反対の声が上がり、ゲイツ氏は辞退した。
教育長官にはリンダ・マクマホン氏を指名した。トランプ氏は「米国は世界のどの国よりも生徒一人当たりの支出が多い」とし、「州に学校を運営させたい」との考えを示した。トランプ氏は教育長官に指名したマクマホン氏に、教育省閉鎖に取り組むよう指示したことを明らかにした。
国防長官にはピート・ヘグセス氏が就任した。ヘグセス氏は保守系TV局のFOXニュースの司会者から登用された。陸軍州兵時代にはイラクやアフガニスタンに派遣されたが、軍や国家安全保障分野の上級職に就いた経験はない。三軍を統帥する国防長官の資質には疑問視する見方がある。
運輸長官にはショーン・ダフィー氏が就任した。ダフィ氏はウィスコンシン州選出の下院議員だった。2019年に辞職した後は、FOXビジネスで司会者を務めた。
第2次トランプ政権の閣僚は、トランプ氏のクローン人間のような人物ばかりだが、これは第1次トランプ政権の失敗に懲りたからだろう。第1次トランプ政権ではその道のプロフェッショナルを指名した。プロフェッショナルたちはトランプ氏の暴走を止めるブレーキ役だったが、本物のプロフェッショナルほどトランプ氏と仕事をすることに嫌気が差してくる。
実際、第1次トランプ政権時代、大統領と対立して国防長官を辞任したジェームズ・マティス氏は退任後、「トランプ氏がいかに何もわかっていないかを危惧し、核のボタンを偽装したモノしか渡していなかった」と語っている。
第2次トランプ政権では同じ轍を踏まないよう、“ミニ・トランプ”ばかりを閣僚に据えた。閣僚が自分のクローン人間なら、トランプ氏は何もしなくてもよい。眠っている間にもちゃんと仕事をしてくれる。しかし、米国民から見ると、トランプ政権の閣僚たちはほぼ全員がアクセル役である。この閣僚名簿を見ると、トランプ大統領の別荘で派手なパーティをやる招待客のリストのようで、とてもホワイトハウスの執務室の面々には見えない。
巨大な権力を手にしたイーロン・マスク氏
その中で唯一、トランプ氏に直言できる人物がいる。新組織である政府効率化省のトップであるイーロン・マスク氏である。マスク氏はもともと民主党寄りだったが、ペイパル創業者のピーター・ティール氏にトランプ氏を紹介されて以来、距離を縮め、2024年の大統領選ではトランプ氏を全面的に支援した。
ただ、マスク氏は自分の興味関心に従っているだけで、トランプ氏に心酔しているわけではない。むしろ「使ってなんぼ」と自分のこだわりを捨てず、いろいろ引っ掻き回し、いつか衝突するだろう。第2次トランプ政権にマスク氏が参加したことは、ブレーキではなく、別のエンジンをもう一つ積んだようなものである。
マスク氏は、連邦政府歳出を年間5000億ドル(訳78兆円)以上の削減を目指し、連邦政府機関の縮小と職員削減に取り組んでいる。この取り組みは、行政サービスの悪化と失業率の上昇につながる。
私が米国に留学していた頃のエピソードである。道端で拾った20ドル紙幣を警察に届けたら、「お前が拾ったなら、お前のものだ。要らないのか? それなら俺がもらっておく」とネコババされた。「地面で拾ったなら(鉱物と同じで)お前が掘り起こしたモノだ」というトーンだった。そう考える米国人が多い。
ということは、落とした人が受け取りに来る可能性も小さいので、仕事を増やしたくなかったのかもしれない。警官は州や郡、市の職員だが、連邦政府機関職員のマインドも同じであろう。コスト削減後、生産性を高めてコスト削減前と同じ成果を出そうという発想はないのであろう。
行政サービスが悪くなっても、インフレが収まればよいと考える有権者もいるだろう。しかし、第2次トランプ政権は逆にインフレを加速するおそれがある。トランプ氏はメキシコとカナダからの全輸入品に25%の関税をかける方針を打ち出している。また、中国に対し10%の追加関税を発動した。
国内の製造業を守るためらしいが、既に米国は国内でものを作る能力を失っているから、関税を高くしても結局は輸入に頼る必要がある。関税を払うのは輸出企業ではなく輸入企業であり、その税収は政府の懐に入る。高く輸入した企業は税金分を価格に転嫁するため、物価は自ずと上がる。
バイデン氏とハリス氏はインフレを抑制できなかった。トランプ氏も自慢の政策を推進すれば同じインフレの道をたどるだろう。これからの4年、米国民の生活はより厳しくなるだろう。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年1月17日号を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



