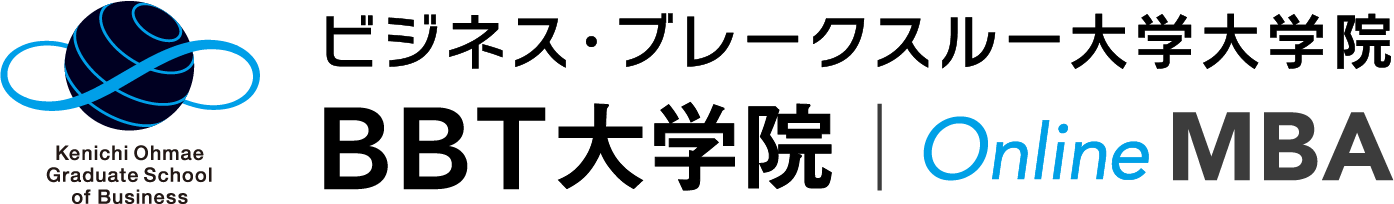AI開発競争は米中2強の争い

大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
中国発の生成AI、DeepSeekが世界に衝撃をもたらしています。米中のAI開発競争が激化することは必至だとBBT大学院・大前研一学長は指摘します。情報統制が厳しい中国で生成AIの精度を高めるのは限界があるという見方が一般的には根強くあります。中国の実力は本物なのか、大前学長の意見を聞きました。
DeepSeekに世界が驚愕
2025年1月、中国のAIベンチャーであるDeepSeekが「DeepSeek−R1」の正式版をリリースした。同社のルーツは梁文鋒(Liang wen feng リャンウェンフォン)氏が立ち上げたヘッジファンド「ハイフライヤー」である。ハイフライヤーはAIを活用して投資をするファンドであり、ファンド運用のためのAI技術開発部門が、後にDeepSeekとなった。
世界のAI開発者を驚かせたのは、「DeepSeek−R1」の開発コストである。AIモデルの開発には、通常、最先端のCPU(中央演算処理装置)とGPU(画像処理装置)を大量に用意してAIのトレーニングを行う。実際、米国企業はNVIDIA製の高性能チップ「H100」を10万基単位で購入して開発環境を整えている。
それに対して、DeepSeekが使用しているのは、もっと安いチップである。米国は安全保障上の理由から、中国に対して輸出規制している。梁氏は規制前に、一世代前のモデルである「A100」を個人で1万基用意した。さらに輸出規制が強化される前にDeepSeekは「H800」を2048基購入した。「H800」はNVIDIAが対中輸出規制を受けて中国向けに開発したチップで、性能は「H100 」に劣り、価格も安い。
これらを使って開発した「DeepSeek−R1」は、オープンAIが2024年9月にリリースしたAIモデル「OpenAI-o1」に匹敵する能力を示した。つまり、低リソースで開発したモデルが、大量のコンピューティングパワーを使って開発された最先端モデルに、遅れることわずか4か月で並んでしまったわけである。
低リソースで開発できたのは、「MoE」と呼ばれる低コスト化技術を活用したからだと言う。こればすべてのDB(データベース)を振り回して答えを追求するOpenAIのやり方に対して、当該部分と思われる部分だけに絞って答えを追求するやり方(「昇華」)で、「さすがに頭がいいな」と唸らされるものである、
一方、「OpenAI‐o1」の大規模な教師モデルを活用する「知識蒸留」(パクリ)を使ったからだという指摘もある。ここで細かな技術的検証はしないが、いずれにしても高性能・高価なGPUを大量に用意しなくて最先端モデルに匹敵するAIを作れたことは確かであり、NVIDIAの株価は大きく下落してしまった。
一連の展開を見て思い出したのは、ソ連崩壊後の米企業の動きである。1980年代、米国では半導体メーカーのインテルが開発に巨額の資金を投じて業界をリードしていた。それで勝ってきたのだから、普通なら物量作戦を続けるところである。
しかしインテルはソ連崩壊直後にモスクワに飛び、郊外に開発者を集めて研究所を設立した。冷戦末期のソ連は物量に乏しく、研究環境も制約が多かった。ただ、制約があるからこそ創意工夫が生まれる。インテルは小さい面積のところに回路を詰め込む創意工夫の知見を欲したのである。実は同じことを、航空機メーカーのボーイングもやり、スホーイやツポレフの技術者を囲い込んでいた。
DeepSeekも、リソースのハンディキャップがある中で創意工夫を積み重ねてきたベンチャーである。圧倒的リソースでAI開発をしてきた米国のビッグテックから見て、無視できない存在になったのは間違いない、
中国躍進の理由は技術者層の厚さにある
DeepSeekは2023年設立の若いAIベンチャーであるが、約2年で開発競争のトップグループに並んだ。中国は全体主義国家で、インターネットに習近平国家主席の悪口は書き込めないし、天安門事件の情報も出てこない。情報統制が厳しい国で生成AIの精度を高めるのは限界があるというのが一般的な見方である。
しかし、2025年1月、レジェンドキャピタルのCIO(最高情報責任者)、Park Joon Sung (パクジュンソン)氏に私が主催する勉強会(向研会)で講演をしてもらってから私の味方が変わった。パク氏はデータを示しながら中国のAI開発が米国に劣後していないことを解説してくれた。例えば、世界の研究機関のAI分野での論文発表件数トップ10のうち、1〜9位は中国の大学や研究機関で、10位にやっと米MITが入る。
ちなみに、梁氏が卒業した杭州市の浙江大学は世界5位である。ほかにも上海交通大学、ハルピン工業大学など、北京大学や清華大学以外の地方大学もいくつかがランクインしている。中央集権の中国で地方の起業家や大学が強くなっているのは注目すべきである。
北京嫌いの経営者や研究者は昔から(杭州市のある)浙江省や江蘇省など中央政府の目が届きにくい地方に集中し、AIの分野ではそれが開花し始めているのかもしれない。また、論文の質はどうか。論文は引用された回数が評価の目安になるが、顔認識では被引用回数トップ5のうち3つが中国の論文である。
なぜ中国でAI研究が盛んなのか。理由の一つとして、そもそも中国には理工系の研究者が多いことがあげられる。理工系学部生は毎年200万人以上で、米国の約6倍である。博士課程修了者は年間5万人弱を輩出し、その数は米国の約2倍である。すそ野が広いだけではない。2022年のAI分野上位2%研究者の出身国を見ると、米国が28%でトップだが、中国は26%と肉薄する。ちなみに3位はインドで7%、4位はフランスで5%である。質の面でも米中が2強であることが良くわかる。
興味深いのは、上位2%研究者の「活動国」である。1位は米国で断トツの57%、2位は中国だが12%で大きな開きがある。このデータは中国出身の優秀なAI研究者の多くが米企業や研究機関で活躍していることを示唆している。実際、OpenAIでAI開発に従事している研究者のうち、約2割が中国出身である。インテルやボーイングが旧ソ連の技術者を囲い込んだように、すでに米国のAI企業の技術者を中に入れているのである。
中国はAIの実装も進んでいる。特に注目したいのはロボティクスとの組み合わせである。北京では、エリア限定ではあるが、自動運転のロボタクシーが走っている。UNITREEの4足歩行ロボットも高性能で、搭載するAIで自己学習や自律探索が可能で、複雑な地形も難なく移動する。軍事用を開発しているのは間違いない。
中国は短期間で一気にAI先進国になった。とはいえ、このまま中国がAI開発開発競争で優位に立つとまでは言えない。実は「DeepSeek‐R1」をリリースした同じ日、北京で李強首相が座談会を開き、そこに招かれた梁氏がスピーチしている。タイミングを考えると、中国政府がDeepSeekを全面的にバックアップすることを国内外に示したと受け取れる。
政府の肝入りでAI開発にお金が集まれば、そこに人も知恵も集まっていく。その意味では追い風である。ただ、それまで創意工夫で取り組んできたところに手厚い支援がつくと、それがかえって足かせになりかねない。旧ソ連の航空機産業も冷戦終結後、技術発展は停滞した。北京と距離があったからできたことも、今後はやりにくくなるだろう。
一方、米国にとって中国の対等はいい刺激になる。トランプ大統領はDeepSeekを、米企業への「ウエイクアップコール」、つまり目覚まし時計と評した。半導体や電力のパワーは依然として重要だが、物量頼りでは足をすくわれかねない。それに気づかせてくれたという点で、DeepSeekには感謝しなくてはならない。米中のAI開発競争の行方はまだ見えてこないが、開発コストが下がることは米企業にとっても恩恵が大きく、競争相手が存在するほうが進化のスピードは増す。今後は開発が一層進むはずである。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年3月21日号を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。