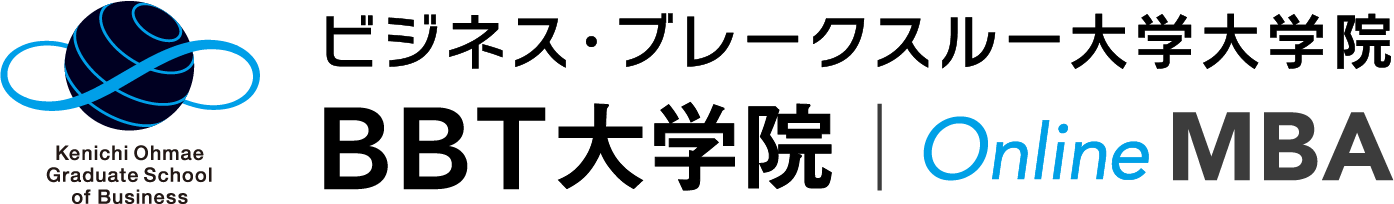身動きが取れない中国不動産不況

大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
約49兆円の負債を抱えている中国の不動産大手・恒大集団が、米国で連邦破産法15の適用を申請しました。恒大集団は「正常な債務再編手続きの一環」と説明していますが、この会社は中国政府が裏で支えているから存続しているだけで、事実上すでに破綻しているとBBT大学院・大前研一学長は指摘します。中国は有効な対策を打ちたくても打てないと大前学長が分析します。
日本が経験した不動産不況よりも深刻
成長を続けてきた中国経済に異変が起きていることは、誰の目にも明らかである。象徴的なのが不動産不況だ。中国の不動産大手「恒大集団」は2023年8月、米国で連邦破産法15条の適用を申請した。恒大集団は2021年に巨額の債務不履行(デフォルト)に陥っており、破綻は時間の問題だった。
また、不況は一企業の問題ではない。同じく不動産大手「碧桂園(へきけいえん)」も負債が膨らみ、デフォルトが危ぶまれている。負債総額は恒大集団が約48兆円、碧桂園が約28兆円で、中国の不動産全体では1000兆円にも上る。また、地方政府のインフラ投資会社「融資平台」では、負債総額が2000兆円に上っているという情報もある。
日本が約30年前のバブル崩壊で経験した不動産不況では、230兆円という国費を救済に使った。負債額は1000兆円なら4倍(または2000兆円なら8倍)違うが、国土の規模を考慮すると、今の中国では当時の日本よりも深刻な不動産不況が起きていると考えていい。
ただ、日本の不動産バブル崩壊とは原因が異なることに注意だ。日本の場合はバブル景気で、不動産価格がどんどん上がった。このままインフレが続けば庶民はマイホームを買えなくなる。そのことが社会問題化して、政府は銀行による不動産への貸し付けを締め付ける、窓口指導と総量規制を行った。それが不動産不況の引き金になった。
その結果、銀行がいくつも潰れた。最盛期には15行もあった都市銀行が3つのメガバンクに集約され、悲惨な状況を招いた。そのダメージは大きく、日本経済は今でも回復していない。
中国の不動産バブルの背景は「先富論」
それに対して中国はどうか。中国の不動産不況が日本のそれと決定的に異なるのは、銀行が介在していないこと。そして買われていた物件が、居住用ではなく投資用である点だ。
中国の不動産バブルの背景には、1970年代後半から中国の改革開放を推し進めたトウ小平の「先富論」がある。「先に豊かになれる人から豊かになりなさい」という意味で、中国人はこれを不動産投資で実践した。
具体的に言うと、先に上海でマンションを買った人が、値上がり後、そのマージン(余力)を使ってマンションを抵当に入れ、浦東など上海郊外に新たな物件を買った。新たに買った物件が値上がりすれば、それを抵当に入れて、また開発中のマンションを買う。それを繰り返すうちに不動産価格の上昇が地方都市に広がり、最初にマンションを買っていた人は金持ちになった。
購入した物件を賃貸に出せるならまだ資金が回りやすい。しかし、中国のマンションは内装を仕上げる前の段階で分譲する。人に貸したければ、オーナーはさらに3割程度追加投資して人が住めるように、水回りなどを整える必要がある。また、そもそも住宅の供給過剰で借り手もいない。地方都市の開発地区は、今やゴーストタウンを意味する「鬼城」と呼ばれている。
日本や米国のように住みたい人がいて、不況の原因が金融機関にあるなら、打つ手はある。しかし、中国の不動産不況は構造が違った。
BATを自由に発展させるのが、有効な打ち手
中国の不動産不況は銀行をつぶしたり、救済しても終わらないが、一つだけ止めるすべがある。景気を、10年以上前のよかった状態に戻すのだ。
当時から不動産価格は上昇していたが、中国経済をけん引していたのは不動産ではなく、BAT(Baidu、Alibaba、Tencent)をはじめとする新興の大企業だ。ところが、自身のコントロールが及ばなくなることを恐れた共産党が締め付けをおこなったことで、新興企業はかつての勢いを失った。
企業の締め付けを緩め、再び活動の自由を与えれば景気が回復して、不動産価格の下落も止まるだろう。ところが、現実にはこれも難しい。新興企業を締め付けた理由でもある「情報統制」を緩めると、習近平国家主席の悪口を14億人の国民がSNSに書き込み始めるからだ。
共産党は、民衆の力で革命を起こして中国を建国した。みんなが表立って共産党批判を始めたら、政権がひっくり返ることを知っている。習氏は、たとえ不況が続いても指をくわえてその様子を見ているしかないのだ。
それはTikTokなどのSNSの解放につながり、共産党独裁に対する不満の声が渦巻くことになる。
つまり、有効な打ち手は共産党の自己否定につながる可能性が高いため、身動きがとれない。“完全独裁”の場合、失敗したらトップは言い逃れができない。失策続きの習近平独裁体制がこのまま続くことはないだろう。
※この記事は、『プレジデント』誌 2023年9月29日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。