高校無償化は国を亡ぼす愚策?
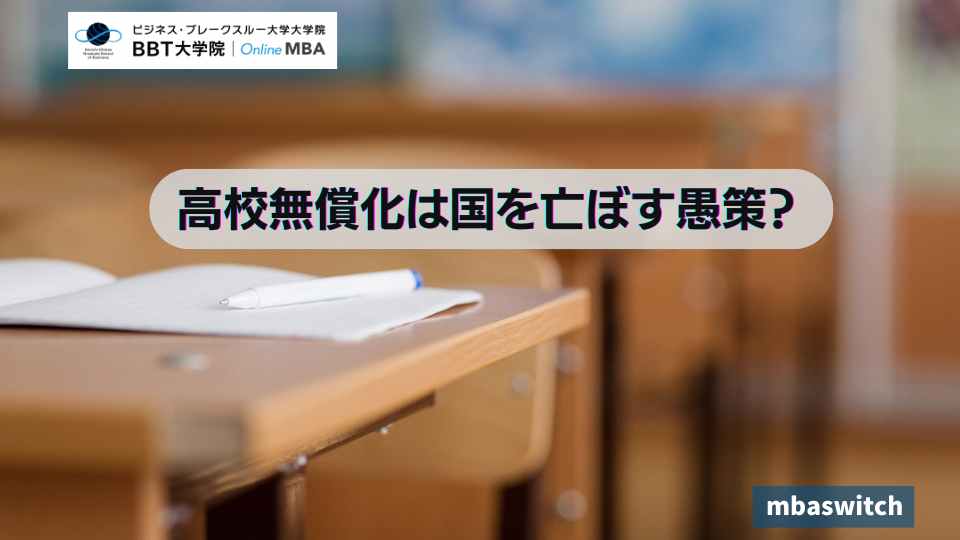
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
2025年度予算案が成立しました。公立高校は実質無償化されることになりました。また、自由民主・公明与党と日本維新の会の3党合意で、2026年4月からは就学支援金の上限額を引き上げ、私立高校も実質無償化される運びです。高校無償化を、BBT大学院・大前研一学長は「拙速だった」と批判、「このままでは国を亡ぼす愚策になる」と警鐘を鳴らします。高校無償化はなぜ国を亡ぼす愚策なのか、大前学長に聞きました。
目先の党利党略だけの理念なき無償化
高校無償化はもともと民主党政権が2010年に実現させた政策だった。ただ、国公立高校に支給される就学支援金の年額11万8800円、そして私立高校に支給される就学支援金の上限額にも所得制限があった。
ここにきて急に事態が動いたのは、2024年10月の衆議院選挙で石破自民党が大きく議席を失ったからである。予算を通すには野党の協力を取り付ける必要があり、維新の会がゴリ押しする高校無償化をのまざるを得なかった。
東京都や大阪府はすでに独自の行政判断で高校無償化を実現している。このことも今回の議論に拍車をかけた。地方からすると、「地方創生を掲げているのに東京と大阪だけ無償化されている現状は不公平」に見える。また、維新の会の地盤である大阪府は財政に余裕があるわけではない。
今回の高校無償化は、国会運営や選挙対策といった国政政党の党利党略、そして財源が乏しい東京都以外の地方公共団体の思惑が重なって成立した。これにより、2025年度予算案が可決され、2025年4月から公立・私立とも所得制限が撤廃されたというわけである。2026年4月から私立高校の支援金については上限を45万7000円に引き上げ、実質無償化になる見込みである。
今回の高校無償化は党利党略で決まっており、本質的な議論は手つかずのままである。無償化と義務教育化は何が違うのか。私立も無償化されるとしたら、公立・私立それぞれの存在意義は何なのか。税金を注ぎ込むのであるから、高校卒業までにどのような人材を育てるべきかといったことも考える必要がある。
成人年齢の話と整合させると、高校まで義務教育化して、最後の1年は社会人教育を行い、卒業すればすべての面において成人と扱えば矛盾なくすっきりする。このように全体のデザインについて議論することなく、目先の党利党略で教育政策を進めていけば必ず歪みが出る。これでは高校義務教育化を提唱する私も批判せざるを得ない。
私立が人気化し、公立が地盤沈下するのは必然
この先、全国の教育現場ではどのような歪みが具体的に発生するだろうか。それは、先行している東京や大阪を見れば予測がつく。
東京と大阪で顕著となっているのは、公立から私立へのシフトである。公立と私立の最大の違いは自由度である。私立はカリキュラムの自由度が高く教員も学校単位で採用を決めることができる。例えば、大学受験対策のために特別な授業をしたり、優秀な教師を高い給料で雇うことも難しくない。我が子に高い学歴を得させたい保護者がどちらを選ぶかと言えば、私立だろう。
高校無償化で学費の障壁が下がれば、公立から私立へのシフトが進むことは確実である。実際、大阪の今年の公立高校一般入試では、府立高校2番手グループである寝屋川、八尾、鳳高校の倍率が1倍を切った。
【資料】
令和7年度大阪府公立高等学校一般入学者選抜(全日制の課程)の志願者数
地方は私立より公立が選ばれる傾向があるが、無償化の開始で公立の地盤沈下が起こり、私立が人気化し公立を逆転していくに違いない。
中学を卒業して職業訓練を受けながら腕を磨いてきた日本の伝統産業も人手不足になるだろうし、高校で勉強するのではなく、友達と群れるだけの不良の溜まり場となる公立高校も増えるだろう。
もっとも、選ばれない学校が淘汰されていくこと自体は悪いことではない。成果を求められるからこそ教育の質が保たれる。
問題は、前述したように公立高校は文部科学省の縛りがきついため、自由度が低く、公立と私立で健全な競争が働かないことである。私立も無償化して公立と同じ土俵に乗せるなら、公立にも私立同様の自由裁量を与えるべきである。
学習指導要領の縛りから学校を解放すべき
さらに言えば、私立も含めて日本の学校は文科省、そして中央教育審議会の決める学習指導要領の縛りから解放すべきである。何をどのように教えるかは、国が一律に決めるのではなく、学校が主体的に決めるべきである。
コンピュータのプログラミングに目覚めた我が大前家の次男は、日本の教育が合わず、中学校をドロップアウトした。渡米してコンピュータ教育に力を入れている全寮制の私学に入学した。しかし、次男はすでにコンピュータ担当の教員よりも腕が良く、「学ぶものがないから退学したい」と言ってきた。私が学校長に掛け合ったところ、学校は新たにIBMのエンジニアを教師として雇ってくれた。
それでも次男は物足りずに文句を言ったが、IBMから来た新任教師は発想が非常に柔軟で、「キミがみんなに教えてみたらどうだろう」と提案した。学校も了承して、次男は高校の2年からITの先生になった。教える側に回って新たな発見があったのだろう。やる気満々で授業に臨むようになり、親として胸を撫でおろしたことを覚えている。
米国の初等中等教育は全体的に崩壊している。ただ、次男が通学した学校のように柔軟性は高く、才能を潰すようなことはしない。その結果、上位校に通う生徒たちはのびのびと育ち、優秀なスペシャリストやリーダーとして国や企業を引っ張っていく人材も出てくる。国としての制度には問題があるが、自由度が高いために優れた学校が生まれる可能性が残されている。
一方、日本の教育はいまだに全員を均質化して平均点を引き上げる工業化社会の教育を行っている。情報化社会、そして今進行しているAI社会では、平均点が高くても特徴がない人材は役に立たない。今、教育に求められるのは個性を伸ばすことである。
学習指導要領は約10年に1回改訂され、学年によっては適用に時差があるため、実質20年に一度しか改訂されてないこともある。直近では2017年に新学習指導要領が告示されたことに伴い、小中学校のプログラミング教育の内容も変わった。しかし、当時は生成AIがまだ世に出ていなかった。
生成AIの登場後はプログラミングのやり方が大きく変わった。にもかかわらず、次の改訂までは古いやり方を教え続ける。そんな馬鹿な話はない。今の社会で活躍する人材を育てるならば、指導要領を3か月に一度の頻度で見直すべきである。
現在の中教審の仕組みでは、3か月どころか1年ごとの改訂でも難しいだろう。それならば、指導の中身は各学校に任せればよい。そうやって各学校が特徴を出したところで本人や保護者が学校を選ぶのである。
学校は何を教えたっていい。もはや指導要領は要らない。今世界で活躍している日本人を見ても、文科省の埒外で育った人ばかりである。日本は料理、アニメ、ゲーム、音楽、建築、スポーツなどの分野でも世界をリードする人材を輩出している。義務教育でこれらのことを専門的に教える学校があってもいい。
学習指導要領で学校を縛り付けたまま無償化しても、高校の大学受験予備校化が進むだけで、AIに代替されることしか学んでいない人材が大量生産されるだけである。そんなことに税金を注ぎ込むことが正しいのか疑問だし、それこそが今一番議論が必要な点なのである。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年4月18日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



